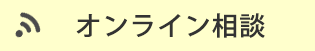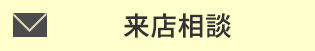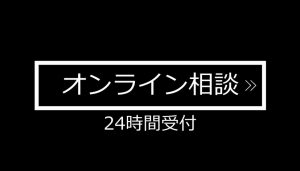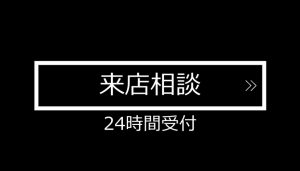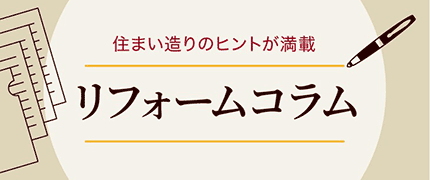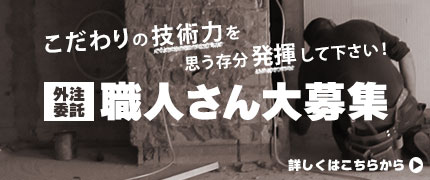私がプライベートで使用している車は、平成2年式です。
つまり35年前の車であり、購入したのは2010年のことです。なので、購入当時既に20年落ちでした。今では、街中でもほとんど見かけなくなったモデルですが、私はこの車をとても気に入っており、いつもそばにいてくれる、言わば相棒だと思っています(笑)。
しかし当然、古い車なので不便もあります・・
今時のような自動ブレーキも有りませんし、燃費だって決して良いとは言えません。また、経年劣化等による不具合も頻繁に起こるので、常に点検整備をして、故障の兆候があればすぐに修理をしてきました。だからこそ、今でも元気に走ってくれています。むしろ、手をかければかけるほど味が出てくるという点では、長年住んできた家と似ているかもしれませんね(笑)。
さて、そんな愛車に乗り続けている私が、いつも疑問に思うのが日本の自動車税制です。
我が国では、車の製造から13年を超えると、自動車税や重量税が高くなる仕組みになっています。古い車に乗り続ける人ほど税金が高くなる・・つまり、まだ使えるから大事にしている人が買い替えを促される構造です。
この税制は、建前上古い車は環境性能が悪いからということになっています。しかし、新車を製造する過程で排出する温室効果ガスと適切に比べた上で導入された税制なのか?私には、新車購入を促す経済的な政策ではないかと思えてなりません。
因みに私の車は、前回のユーザー車検の際に、「排出ガスが現在のエコカー並みですね!」と、検査官に驚かれるほどクリーンな状態でした。実際、現在の整備技術があれば、排ガスも問題なくコントロール出来ますし、安全面でも法的基準をクリアしていれば余裕で車検に通るのです。
それなのに、年式だけで機械的に課税される・・これは果たして公平な制度でしょうか?
甚だ疑問です。
さて一方、国は住宅政策において「ストック型社会の実現」を掲げています。
中古住宅の流通促進、リフォームの支援、長期優良住宅の推進等、今あるものを活かす方向に舵を切っています。私達のようなリフォーム業者も、その理念のもとに日々仕事をしていることは、前回のブログでもお話しした通りです。ところが、車に関してはまったく逆。古いものは増税、新しいものは優遇・・これでは国として一貫性がありません。
欧米では、古い車を文化的資産として扱う国が多いと言います。
イギリスでは40年超のクラシックカーに税金が掛からない制度がありますし、ドイツでは車の年式ではなく、排気ガス性能や走行距離、整備状態に基づいて課税される仕組みだそうです。大切に乗っているという姿勢そのものが、社会的にも認められているのです。我が国も、このようなスバラシイ考え方を是非見習うべきです。
家と車、どちらも人生の時間を共にする「大切なストック」です。
私はどちらも大切にしながら長く使うことが、これからの日本にとって自然で、持続可能な価値観だと信じています。
新しいものを次々と買い替えるのではなく、今あるものに手を入れながら、丁寧に使っていく。
そうした暮らし方こそが、本当の意味での豊かさに繋がるのではないでしょうか?
代表取締役 松戸 明