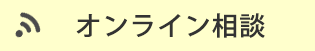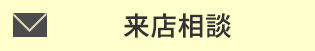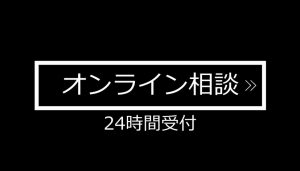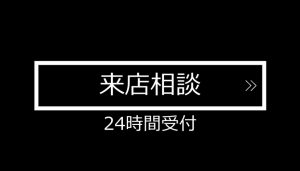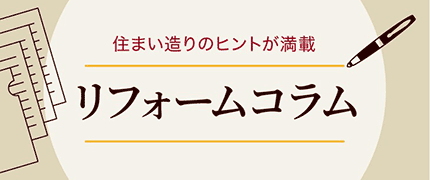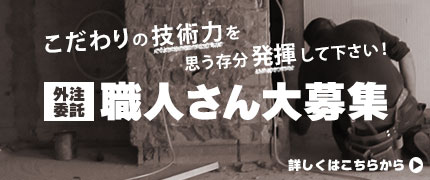宅地建物取引業法が改正された(2018年4月)ことにより「ホームインスペクション」に注目が集まっています。これから中古物件を売買するご予定の方は、実施をご検討されているかもしれませんね。
とは言えまだまだ認知度が低く、周知されていないサービスですので「ホームインスペクションって、いつやるの?」とか「どんな流れで進むの?」と疑問やご不安をもたれている方も多いでしょう。
本稿では、ホームインスペクションを実施するタイミングや流れについて詳しく解説していきます。注意点もご紹介しますので、実際にホームインスペクションを実施されるときの参考にしてください。
ホームインスペクション(住宅診断)を実施するタイミング
まず、ホームインスペクションを実施するタイミングについてご説明します。この「タイミング」は、物件の種類(中古物件、新築分譲住宅、新築注文住宅)によって違いますので、個別にご紹介していきます。
中古住宅の買主の場合
中古住宅は、買主と売主にわけてご紹介しましょう。まずは買主からです。買主がホームインスペクションを入れる理想のタイミングは「購入申込後、売買契約を締結する前」です。
- 内見(内覧)しながら購入物件探し
- 買いたい物件が決まったら「購入申込書(買い付け申込書)」を出す
- ホームインスペクションを実施
- 売主と価格や引き渡し日などの条件をつめ「売買契約」
- 引き渡し日に代金を清算して所有権移転登記
- 必要なリフォームを済ませてお引っ越し
「売り出し中」の中古物件は、売主宛に②の「購入申込書」を出して受領してもらうことで「商談中」に変わります。「売り出し中」のままだと、いつ他の購入希望者に先を越されるかわからない状態です。
ですから、まず買いたい物件を決めて「購入申込書」出すことが最優先です。さらに契約前であれば、ホームインスペクションの結果「売買価格に見合わない重大な問題」が見つかったとしても以下の選択ができます。
- 購入中止
- 修繕依頼
- 値下げ交渉
「購入申込書」は契約書と違い、法的な拘束力を持ちません。まんがいちホームインスペクションで重大な問題がみつかれば、違約ペナルティを受けることなく購入を中止できます。


どうしても欲しい物件であれば購入を中止せず、売主に修繕を依頼する方法もあります。もしくは修繕せず、住宅の状態に見合った価格まで値下げしてもらい購入するのもよいでしょう。
フルリノベーション(スケルトンリノベーション)を実施される方は、ホームインスペクションを入れる必要性が低いです。劣化や腐朽が見つかったとしても、構造駆体以外はすべて解体撤去するので問題ありません。
なお、リノベーションについては以下の記事で詳しく解説しています。ご興味がある方は、あわせてご覧ください。
残念ながら、ホームインスペクションを入れることを嫌がる売主や不動産屋もいます。拒否された場合は、以下の選択肢から次の行動を選ぶことになります。
- 粘り強く交渉する
- ホームインスペクションなしで買う
- 購入をあきらめる
ホームインスペクションでわかるのは、住宅の劣化状況だけではありません。購入後におこなうリフォームの規模や、将来必要なリフォームの時期の参考にもなります。実施の方向で検討されることをおすすめします。
中古住宅の売主の場合
中古住宅の売主がホームインスペクションを入れる場合は、売り出すと決めたらできるだけ早いほうがいいでしょう。ただし、買主に任せるという選択肢もあります。
売主や売主側の不動産屋が作成したインスペクション報告書は買主に信用されにくいので、それならいっそのこと買主にお任せするほうがいいでしょう。


なお、買主からの調査要望を断るのは得策ではありません。民法改正(2020年4月1日施行)により売主に「契約不適合責任」が課せられるようになりましたので、できるだけ瑕疵を発見して対応しておくほうが安心です。
詳しくはインスペクションのメリットを解説した以下の記事でご紹介しています。気になる方は、あわせてご覧ください。
建売住宅や分譲マンションの買主の場合
新築の建売住宅や分譲マンションは、中古物件と同じく「購入申し込み後、売買契約を締結する前」が理想的です。契約内容を満たさない問題が見つかったら、購入を中止するか補修を依頼するといいでしょう。
契約してから引き渡しまでに実施する場合は、書面や写真で補修箇所を明らかにして、必ず修正を確認してから引き渡しおよび代金清算に移ってください。引き渡し後の対応がいいかげんになる売主もいますので、要注意です。
一般的には引き渡し前に内覧会(買主検査)を開催してくれますので、そのときにインスペクター(住宅診断士)にも来てもらうといいでしょう。
新築注文住宅の施主の場合
新築注文住宅は、建築中に複数回のホームインスペクションを実施するのが理想です。たとえば、以下のタイミングで検査できると安心です。
- 基礎の配筋後
- 構造駆体の金物取り付け後
- 断熱材施工後
- 外壁下地合板施工後
- 完成後
基礎の配筋や構造駆体の金物、断熱材、外壁下地は完成すると隠れてしまいます。非破壊で確認できるチャンスは建築中だけですので、ぜひチェックしておきたいところです。
完成後だけホームインスペクションを入れる場合は引き渡し前に調査してもらい、修正が完了してから引き渡しと代金の清算を実行しましょう。
注文住宅も完成後に内覧会(施主検査)を実施するのが一般的です。そのときに調査してもらうといいでしょう。
ホームインスペクション(住宅診断)の流れ
つづいて、一般的なホームインスペクションの流れをご紹介します。なお、事業者によって多少手順が変わりますので、詳しくは依頼する事業者にご確認ください。
ホームインスペクションの流れは、以下のとおりです。
- ホームインスペクション事業者(インスペクター)に問合せ
- 購入物件決定(中古や分譲の場合)
- 概算見積もり請求
- 依頼
- ホームインスペクションを実施
- 調査結果報告書の受領
順番に、もう少し詳しく解説します。
ホームインスペクション事業者(インスペクター)に問合せ
まずは、ホームインスペクションをしてくれる事業者(インスペクター)探しからです。以下の3つを確認しながら、2~3社ほど比較して決めるといいでしょう。
- 調査内容
- 費用
- 予約の空き状況
調査内容は、とても大事です。リストや報告書のサンプルを見せてもらい確認しましょう。


費用は基本検査項目だけでなく、オプション検査項目も確認しておきましょう。たとえば、以下の検査は基本検査に入るのか、オプションなのか。オプションならいくらかかるのか、聞いておくと安心です。
- 床下
- 屋根裏
- 屋根
- 機器を使った検査
ホームインスペクションは、基本的に目視でおこないます。サーモグラフィを使った断熱材検査やドローンを使った屋根検査など、機器を使った検査はオプションの事業者が多いでしょう。
購入物件決定(中古や分譲の場合)
中古物件や新築分譲住宅は、購入したい物件が決まったら「購入申込書」を出しておきましょう。出さないと、インスペクションを実施している間に他の購入希望者に買われてしまいます。
建物概要や間取りがわかったら、インスペクターに伝えて概算見積もりを依頼しましょう。
概算見積もり請求
ホームインスペクションの費用は建物の種類や大きさで変わりますが、相場はおおよそ4~7万円くらいです。マンションのほうがやや安く、一戸建ての床下や屋根、小屋裏(屋根裏)も調査すると6~12万円くらいかかります。
建築中の注文住宅の検査は、別途費用がかかるのが一般的です。配筋や金物、断熱材なども検査しておきたい方は、あわせて見積もりしてもらいましょう。
複数社を比較検討したい方は、このタイミングでどの事業者に頼むか決定しましょう。1社に依頼を打診して、インスペクション実施日を調整していきます。
依頼
ホームインスペクション実施日時の調整は、以下のメンバーでおこないます。
- 中古住宅や分譲住宅 ⇒ 買主、売主、不動産屋、インスペクター
- 新築注文住宅 ⇒ 施主、建築会社、インスペクター
調査実施日までに必要書類をインスペクターに確認して、メールやFAXで速やかに送信しておきましょう。できれば平面図(寸法が入った精密な間取り図)は準備したいところです。その他、以下の図面や書類もあると役立ちます。
項目 | あると役立つ図面・書類 |
一戸建て | 平面図、基礎伏図、立面図、矩計図、建築確認の年月日がわかる書類(※1) |
マンション | 平面図、建築確認の年月日がわかる書類、長期修繕計画表、過去の修繕履歴(※2) |
既存住宅瑕疵保険を利用する場合 | 検査済証の発行年月日が確認できる書類 |
※1 建築確認の年月日が分かると、建物が持つ耐震性能の目安になります。
※2 修繕は適切におこなわれているマンションは、屋上の防水検査を省略できます。
ホームインスペクションを実施
ホームインスペクション当日、一般的には以下の順序で調査していきます。検査時間は、30坪程度の一戸建てでおおよそ3時間くらいです。(ただし、売主や建築会社から順序の指定があった場合は、この限りではありません)
- 建物外部の調査
- 建物内部の調査
- 床下・屋根裏の調査
それぞれの詳細な調査箇所もご紹介しましょう。後述の項目は、国土交通省が定めた調査基準がもとになっています。
調査場所 | 調査項目 |
建物外部 | 敷地周辺、基礎、外壁、屋根、軒裏、雨樋、バルコニー、玄関ポーチなど |
建物内部 | 床・壁・天井、建具(扉・窓)、内装材、設備、雨漏りなど |
床下・屋根裏 | 基礎、シロアリ、土台・床組み、配管、雨漏り、断熱材など |
参考:国土交通省告示第八十二号
新築の建築中検査は、工事現場のタイミングに合わせて都度実施します。例えば配筋検査なら、配筋設置からコンクリートを流し込むまでの間。構造駆体の金物検査なら、金物設置から内装下地を張るまでの間に実施します。
調査結果の概要は調査と同時進行でインスペクターから聞くとわかりやすいですが、最後にまとめて聞いてもOKです。
調査結果報告書の受領
ホームインスペクションが完了した数日後、詳細な調査報告書がもらえます。報告書の内容にわからないところがあれば、しっかり確認しておきましょう。大事なことなので、遠慮せず積極的に質問することをおすすめします。
報告書の受領と同時に調査代金を支払います。これで、ホームインスペクションは終了です。物件購入の判断や補修依頼、リフォーム計画の策定にお役立てください。
なお、既存住宅瑕疵保険を利用される場合は、調査で要件をクリアしていることを確認したのち、保証書が発行されるまで約2~3週間かかります。引き渡し後は申し込みができませんので、ご注意ください。
まんがいち、調査の結果「既存住宅瑕疵保険不適合」となった場合は、不適合箇所を補修工事したうえで再検査を行い適合すればOKです。
ホームインスペクションの流れまとめ
ホームインスペクションは、調査を依頼するインスペクター(住宅診断士)を決め、調査する物件が決まったら日程調整や書類の準備をして、当日の調査に至ります。調査後に報告書を受領して代金を清算したら、すべて完了です。
ホームインスペクションを入れるタイミングは、物件の種別によって違います。中古物件や分譲住宅は「購入申し込み後から、売買契約の締結前」が理想で、新築住宅は建築中から調査を開始するのが理想です。
ホームインスペクションを実施することで、安心できるだけでなく、中古や分譲物件の状態に見合った適正価格で購入できます。注文住宅であれば、施工不良の家に住まなくて済むでしょう。これから住宅を購入される方は、ぜひご検討ください。
弊社では、弊社の仲介や「中古物件購入+リノベーション」をご利用いただいたお客様を対象に、無料でホームインスペクションを実施するサービスを準備しております。ご興味ある方は、以下をご覧ください。
▼おすすめの関連記事
》ホームインスペクションのメリットとデメリット
》ホームインスペクション費用の相場
》ホームインスペクションとは